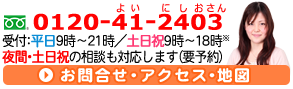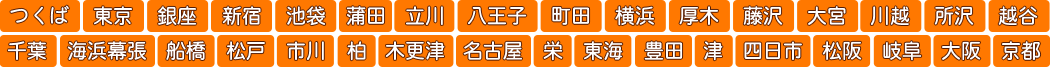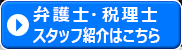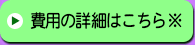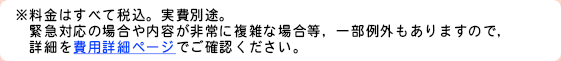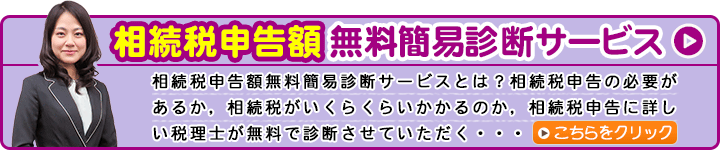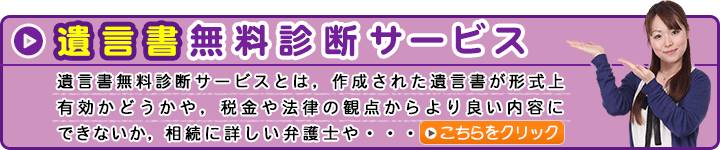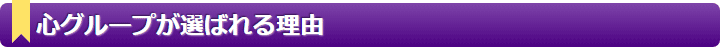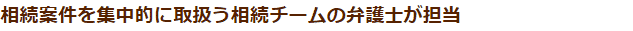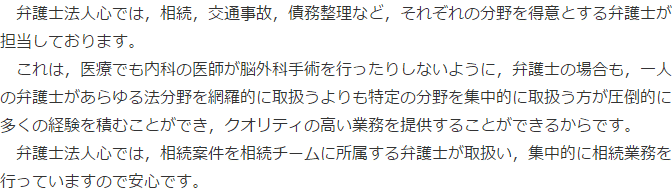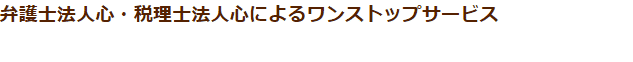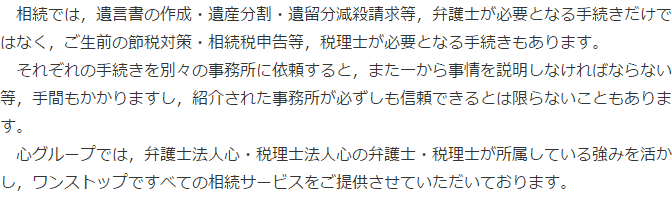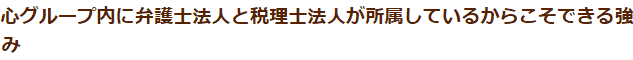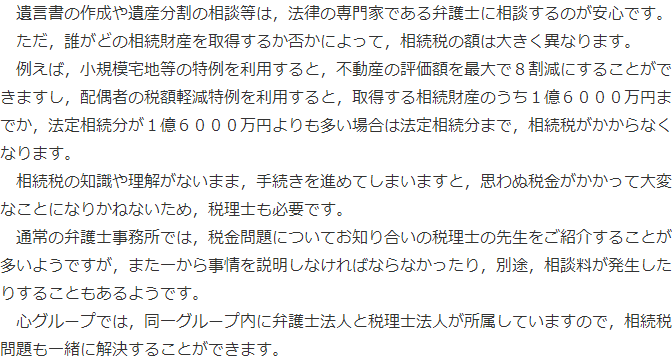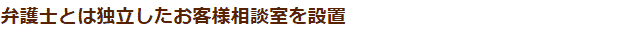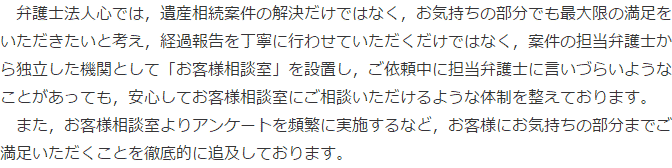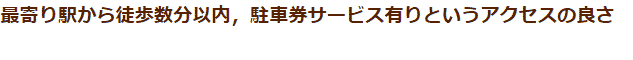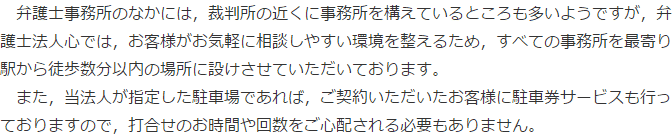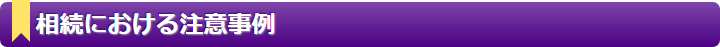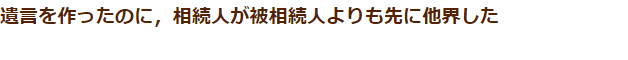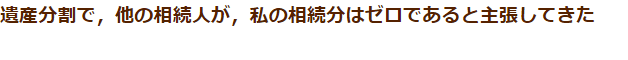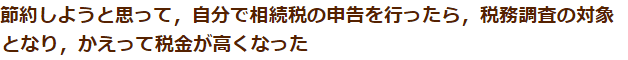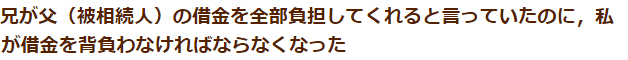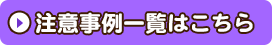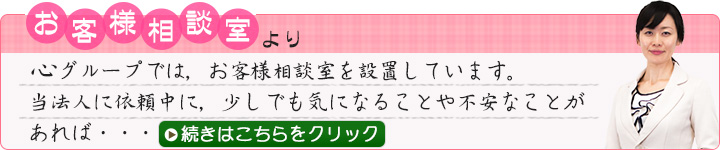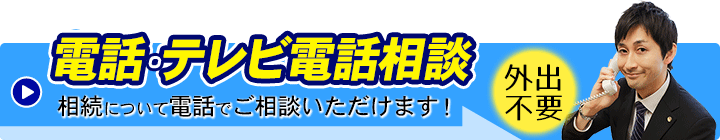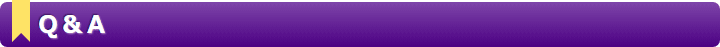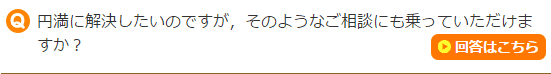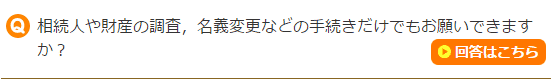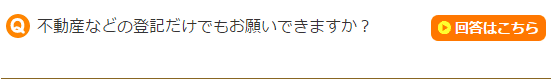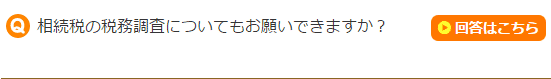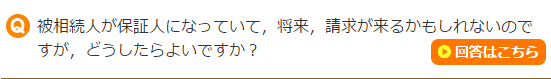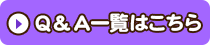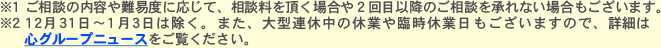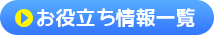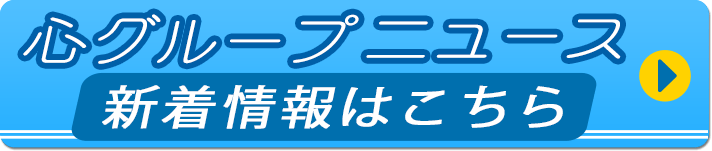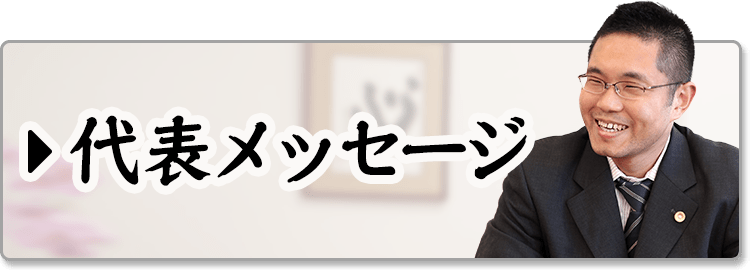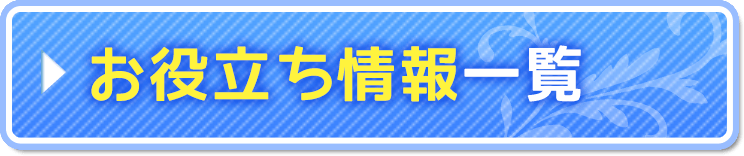伊勢にお住まいの方で相続にお悩みの際は
相続を集中的に扱っている専門家がご相談を伺います。相続に関する様々なご相談を承っておりますので、お悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
相続での注意点
相続では、気を付けなければならない事項が多くあります。相談料は原則無料ですので、伊勢にお住まいの方で相続が発生した際には、お気軽にご相談ください。
お問合せはフリーダイヤルで
フリーダイヤルの番号や、事務所の場所などを掲載しております。メールフォームからもお問い合わせいただけますので、お気軽にご連絡ください。
相続のご相談から解決までにかかる時間
1 相続の流れ

相続の流れは、おおむね、以下のとおりになります。
① 相続人調査、相続財産調査
② 遺産分割協議
③ 払戻、名義変更の手続
ここでは、それぞれの手順を踏むのに必要な時間を説明し、相続が解決するまでにかかる時間を説明したいと思います。
2 相続人調査、相続財産調査にかかる時間
相続人調査では、誰が相続人になるかを公的な記録で調査する必要があります。
公的な記録は、ほとんどの場合、市区町村役場が管理している戸籍になります。
わざわざ調べなくても相続人が誰かが明らかだと思われる場合であっても、万一のことを考えると、戸籍の調査を行った方が良いと考えられます。
また、払戻、名義変更の手続を行うにあたっては、法務局や金融機関、証券会社に対し、相続人が誰であるかを戸籍で証明することが求められます。
このため、戸籍を取得して相続人を調査することは、必須の流れとなります。
同様に、どのような相続財産が存在するかを確認することも、遺産分割協議や払戻、名義変更の手続の大前提となります。
相続財産調査も、最初に行うべき必須事項となります。
相続人調査に要する時間は、相続人の人数、続柄、これらの人の本籍地の動き次第によって異なります。
早いと、1日で必要な戸籍を取得することができることもありますが、多くの場合は、数週間の期間を要します。
被相続人の兄弟姉妹、甥姪が相続人となっていたり、複数回の相続が発生していたりすると、数か月の期間を要することもあります。
相続財産調査に要する時間は、財産の手がかりが自宅等に残されているのでしたら、数日で終えることができることもあります。
他方、手がかりが残されておらず、総当たりで調査を行う必要がある場合は、数か月の期間を要することもあります。
3 遺産分割協議にかかる時間
相続では、相続人全員が、どの財産を誰が取得するかについて、話し合いを行い、合意する必要があります。
相続人が1人でしたら、遺産分割協議を行う必要はありませんが、相続人が2名以上いる場合には、必ず、相続人全員での合意を行う必要があります。
遺産分割協議にかかる時間は、相続人同士の関係、それぞれの意見の内容次第で変わってきます。
すぐに相続人の意見を確認することができ、相続人同士の意見対立がないのでしたら、1日で遺産分割協議を終えることもできますが、このようなことは少ないでしょう。
意見対立が生じなかったとしても、相続財産に関する情報を共有し、遺産分割の方法を検討するのに、数週間程度の時間が必要と考えた方が良いです。
相続人同士の意見対立が深刻である場合は、それを調整するのにかなりの時間が必要になることがあります。
最終的に意見調整ができず、家庭裁判所の手続を用いることとなった場合は、早くても数か月、長いと年単位の時間が必要になります。
4 払戻、名義変更の手続にかかる時間
遺産分割の方法について合意が成立すると、次は、不動産や預貯金、有価証券の払戻、名義変更の手続を行うこととなります。
この手続に要する時間は、財産の種類、手続を行う機関によってまちまちですが、1か月程度の期間が目安となります。
ただし、財産の種類が複数ある場合は、さらなる時間が必要となることもあります。
相続について弁護士に相談するべきタイミング
1 弁護士への相続相談

相続について弁護士に相談するべきタイミングは、どのような内容の相談をするかによって変わってきます。
ここでは、場面毎に、弁護士に相談するべきタイミングを説明したいと思います。
2 相続の生前対策
相続について、あらかじめ生前に対策を行っておくことがあります。
弁護士に相談する場合としては、将来、紛争が生じないように対策を打っておくことが考えられます。
具体的には、遺言を作成し、どの財産を誰が取得するかを決めておくことが考えられます。
生前対策については、何らかの対策をとろうと思い立った段階で弁護士に相談するのが良いのではないかと思います。
というのも、そのうち誰かに相談しようと考えていると、結局、誰にも相談しないままになってしまうことが起こるからです。
何の生前対策も行わずに、あとで後悔するような事態が生じないようにするためにも、思い立った段階で相談するのが良いでしょう。
3 相続発生後
相続が発生すると、相続人間の意見調整、相続財産の名義変更等、様々な対処を行う必要があります。
しかし、相続発生後の段階では、何にどのように対処したら良いのか分からないということが多いのではないかと思います。
このような場合には、漠然とした質問で構いませんので、弁護士に、今後、どのように行動すれば良いのかを質問するのが良いのではないかと思います。
とはいえ、相続発生の直後だと、故人が亡くなられたことのショックもありますし、葬儀、法要もありますので、すぐに相談することは現実には難しいのではないかと思います。
このため、葬儀や法要がある程度落ち着いた段階で、弁護士に相談するのが良いのではないかと思います。
4 紛争の顕在化
相続について、相続人間の意見対立が大きく、紛争が顕在化することがあります。
このような場面は、弁護士に相談する必要性が特に大きいと言えます。
紛争が顕在化した段階では、顕在化が明らかになり次第、速やかに弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
弁護士に相談すると、どのように相続人間の話し合いを行うべきかの助言を得ることができ、今後の方針を立てることができます。
また、早期に弁護士が関与することにより、不利な相続にならないよう、必要な対処を行うことも期待できます。
例えば、紛争の初期の段階では、どのように証拠を保全するかが重要になってきます。
早期に弁護士に相談すると、残すべき証拠は何か、どのように証拠を保全するべきかを確認することができ、証拠保全に向けた行動をとることもできるようになります。
不動産の取り扱いを得意とする専門家にご相談を
1 相続と不動産

相続の場面では、不動産の問題が出てくることがしばしばあります。
状況によっては、被相続人が所有・居住していた不動産の売却を検討することもあるでしょう。
また、被相続人が所有していた不動産を引き継ぐ代わりに、他の相続人に代償金を支払うことも考えられます。
こうした場面では、不動産に強い専門家に相談することをおすすめします。
ここでは、不動産の売却を検討する場面について、どのような専門家に相談すべきかを説明していきたいと思います。
2 不動産の売却を検討する場合
被相続人が所有していた不動産を利用する予定がなく、不動産の管理にも不安がある場合は、不動産の売却を検討することがあります。
このような場面では、不動産仲介業者に依頼し、不動産の買手を探してもらうことになります。
不動産仲介業者に依頼する場合には、専門家が不動産仲介業者と連携して行動すべき場面があります。
たとえば、不動産を売却するときには、それに先立って不動産の名義変更を行う必要があります。
この場合には、不動産仲介業者と協議の上、いつまでに遺産分割協議をまとめて相続登記を行うかを検討する必要があります。
また、不動産を売却して相続税の納付に充てる場合には、基本的には、相続開始後10か月以内に売却手続きをし、売却代金の入金まで完了している必要があります。
このような場合には、不動産仲介業者と協議の上、限られた期間内で、いくら以上で売却する必要があるかを検討しなければなりません。
このように、相続の場面では、不動産仲介業者と専門家が連携すべき場面がしばしばあります。
連携が不十分であると、売却までに不動産の名義変更が行えなかったり、相続税の納付の期限までに不動産の売却代金の入金が間に合わなかったりするおそれがあります。
3 不動産に強い専門家にご相談ください
以上から、相続問題は、不動産仲介業者と十分に連携できる専門家に相談するのが望ましいことがあります。
私たちも、不動産仲介業者との連携に力を入れて取り組んでおりますので、相続についてお悩みの方はご相談ください。
不動産評価に強い専門家に相談すべき理由
1 相続と不動産評価

相続の場面では、不動産をどのように評価するかは、重要な課題になってきます。
特に、弁護士、税理士にとっては、不動産をどのように評価するかは、結論を大きく左右します。
以下では、それぞれの専門家にとって、不動産評価が結論にどのような影響を及ぼすかについて、説明したいと思います。
2 弁護士と不動産評価
弁護士は、特に遺産分割や遺留分侵害額請求の場面で、不動産評価を行う必要があります。
不動産評価の結果次第で、相手方から支払を受ける金額、相手方に支払う金額が、大きく変わってくるからです。
不動産の評価は、正確に行うのであれば、不動産鑑定士に依頼し、評価額を鑑定してもらいます。
しかし、現実には裁判所の鑑定により選任された不動産鑑定士でない限り、不動産鑑定士の中立性が担保されているとは言えないという問題があります。
また、裁判所の手続が進められている場合であっても、家庭裁判所は、必ずしも、鑑定手続を実施するとは限りません。
裁判所が、双方の主張の中間値を採用する等し、鑑定手続によらない評価を図ることもあり、不動産鑑定士に鑑定を依頼するまでに至ることは、稀であると言えます。
このため、弁護士にとっては、鑑定以外で何らかの合理的な評価方法を策定し、その評価結果に基づき、相手方との交渉を説得的に行うことが重要になってきます。
実務上は、不動産仲介業者に協力を依頼し、査定書を作成する、公示地価、路線価、固定資産評価額等を参照し、評価額を算定する等の対応を取ることが多いです。
3 税理士と不動産評価
税理士は、相続税等の申告の場面で、不動産の評価を行う必要があります。
不動産評価の結果次第で、相続財産の総額が変動し、納付すべき税額も変動してくることとなります。
相続税等の申告では、不動産の評価方法は、財産評価基本通達等に記載されたルールにしたがって行います。
こうしたルールの中には、不動産を特別に減額することを認める内容のものがあります。
ところが、詳しくない税理士であれば、このようなルールの存在を知らないこともありますので、不動産を特別に減額できる場合に該当するかどうかの判断は、税理士によって大きく異なる可能性があります。
4 不動産評価に強い専門家に依頼すべき
このように、不動産評価をどのように行うかは、結論に大きく影響します。
不利にならない解決とするためにも、不動産評価に強い専門家に依頼することをおすすめします。
相続で困った場合の相談先
1 相続に関与する専門家

相続に関与する専門家は様々です。
様々な専門家のうち、どの専門家に相談すべきかは、現在問題となっている内容やお困りの内容によっても異なります。
ここでは、それぞれの専門家に、どのような問題について相談すべきかを説明したいと思います。
⑴ 弁護士
弁護士は、法律の専門家ですので、法律問題全般について関与することがあります。
その中でも、弁護士にしかできないものの代表例は、相続人間の意見調整です。
相続人間で意見対立がある場合は、法的紛争があることとなりますので、弁護士しか関与できないこととなっています。
このように、相続人間の意見調整が必要な場合は、弁護士に相談すべきでしょう。
⑵ 税理士
税理士は、税金の専門家ですので、相続税申告等の税金の手続に関与します。
こうした税金の問題は、税理士しか関与できないこととなっています。
相続税申告が必要な場合は、税理士に相談すべきでしょう。
⑶ 司法書士
司法書士は、登記の専門家ですので、不動産の名義変更に関与します。
司法書士以外では、弁護士も登記申請を行うことがありますが、多くの場合は、司法書士が登記申請を行っています。
登記申請が必要な場合は、司法書士に相談することが多いでしょう。
2 相続問題の相談先
このように、各専門家は、それぞれが主として関与する分野をもっています。
とはいえ、現実には、複数の問題が絡み合っていることも多いです。
例えば、相続人間の意見調整を行いつつ、相続税申告を行わなければならないこともあります。
また、そもそも、どのような問題が生じる可能性があるのかを判別し難いこともあるでしょう。
この点を踏まえると、複数の領域をカバーしている専門家か、複数の専門家が連携して対応することができる相談先に相談するのが望ましいのではないかと思います。
私たちは、各分野の専門家が連携してご相談に対応する体制を作っています。
相続問題についてお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺産分割についてお悩みの方へ
1 遺産分割の難しさ

遺産分割においては、亡くなった方が所有していた財産を、相続人間でどのように分けるかを決めなければなりません。
遺産の大部分が預貯金等の金融資産の場合は、残高を割算して、各自の取得額を算定することができますが、遺産の大部分が不動産等の場合は、各自の取得分をどのように調整するかについて、協議を重ねる必要が出てきます。
ここでは、不動産等について、どのような分割方法が用いられるかについて、紹介を行いたいと思います。
2 現物分割
現物分割は、個々の財産をそのまま分割する方法で、一つ一つの財産について、相続人の誰が取得するのかを決めていくことになります。
土地や建物については、一部を分筆した上で、相続人に取得させることもあり、この場合には、分筆登記の手続きを行う必要があります。
この方法を用いれば、財産の現状を維持することができますが、実際には、それぞれの相続人が取得する財産が相続分におおむね等しくなるようにすることが困難である場合が多いです。
そのような場合には、次の代償分割を検討することになります。
3 代償分割
代償分割は、一部の相続人が、相続分を超える額の遺産を取得し、その代わりに、他の相続人に対して、代償金を支払う方法です。
財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。
例えば、事業を承継する予定の相続人に事業用財産を単独で承継させたい場合や、建物に居住している相続人に建物を単独で承継させるのが適切である場合などに、代償分割が利用されることがあります。
代償分割においては、代償金を負担する相続人に資力があるかどうかが問題となることが多いです。
4 換価分割
遺産を第三者に売却し、売却代金を相続人間で配分する方法を換価分割といいます。
遺産分割協議においては、相続人同士で、遺産の売却方法についても、合意をする必要があります。
相続財産を現金化することにより、個々の財産の評価額に影響されることなく、自由に分割することができます。
しかし、遺産を売却してしまうため、被相続人の財産をそのままの形で利用することはできなくなります。
5 共有分割
共有分割は、遺産を複数の相続人で共有する方法です。
共有状態が継続することにより、将来において紛争の火種となる可能性があるため、相続人間に争いがない場合に限った方が良いとされています。
6 遺産分割についてのご相談
このように、遺産分割では、複数の分割方法を検討し、相続人全員が合意できる分割方法が何であるかについて、協議を重ねる必要があります。
どのような分割方法が適切かについては、ケースバイケースになる部分もありますので、専門家にご相談いただいた方が良いことも多いと思います。
遺産分割についてのご相談がありましたら、お問い合わせください。
相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄には期限がある

相続放棄は、基本的に、相続の開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。
相続の開始を知った時から3か月が経過すると、単純承認したものと扱われ、被相続人のプラスの財産とマイナスの債務を引き継いだものとされてしまいます。
なお、3か月の期間については、初日不算入で計算することとされています。
したがって、相続の開始を知った日が2月26日の場合は、5月26日までに、相続放棄の申述書を管轄権のある家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所が夜間窓口を設けている場合は、5月26日の午後11時59分までに申述書を夜間窓口に提出すれば、期間内に申述を行ったものと扱われます。
2 いつから3か月以内に手続を行う必要があるか
3か月の期間の始まりは、相続の開始を知った日であり、被相続人が亡くなった日ではありません。
このため、被相続人と交流がなく、被相続人が亡くなった事実を長期間知らなかった場合には、実際に被相続人が亡くなったことを知った時から、3か月の期間が計算されることとなります。
実際、被相続人が亡くなってから10年後に相続の開始を知った事案でも、相続放棄の申述が受理された例があります。
また、相続が開始したこと自体は知っていたが、被相続人に財産も負債も全く存在しないと信じていた場合にも、相続放棄の申述が認められる可能性があります。
この場合には、被相続人の財産、負債の存在を知ってから3か月間が、相続放棄の申述が認められる期間になります。
もっとも、基本的に、家庭裁判所は、被相続人が亡くなった時点で、相続人が相続の開始を知っていた可能性があるのではないかと考えます。
こういったことから、被相続人が亡くなって長期間が経過してから相続放棄の申述が行われた場合には、家庭裁判所に、具体的な事情を説明する必要が生じてきます。
場合によっては、審問に付されることとなり、家庭裁判所への出頭が求められたり、被相続人との生前の交流状況等の調査が行われたりする可能性があります。
こうした事案では、あらかじめ、申述書とともに、被相続人との生前の交流状況等を記載した書面を提出した方が良いこともあるでしょう。
3 相続放棄に関するご相談
以上のとおり、相続放棄には期限がありますので、なるべく早く相談されることをおすすめします。
また、被相続人が亡くなってから長期間が経過した後の相続放棄については、家庭裁判所にどのような説明を行うかについて、検討を要することがあります。
これらの点につきましては、専門家にご相談いただいた方が良いものと思います。
遺言についてお悩みの方へ
1 遺言を作る意味

遺言は、思いどおりの相続を実現するための手段です。
例えば、個々の相続財産について、相続人の間でどのように分けるかを決めておくことができます。
決め方によっては、ある相続人については多めに、ある相続人については少なめにというように、財産を分けることもできます。
さらに、相続人以外の方に財産を分けることもできます。
遺言を作る意味は、これだけにとどまりません。
遺言を作ることによって、相続が始まった後に、相続人の間で紛争が起きることを、事前に防ぐことができます。
遺言がない場合は、相続が始まると、財産の分け方を決めるために、遺産分割協議をしなければなりません。
協議がスムーズにまとまる場合は良いのですが、まとまらなければ、遺産の分割方法を巡って、調停や審判で長期間にわたって争うことも、しばしばおこります。
特に、事業を承継させる必要がある場合には、いったん紛争が起きてしまうと、事業に支障をきたし、事業を続けることが困難になることもあります。
そこで、遺言を作り、遺産の分割の仕方をあらかじめ決めておけば、このようなトラブルを事前に避けることができるのです。
2 遺言の作成について
遺言は、自分で自筆することにより、作ることができます。
これを自筆証書遺言といいます。
しかし、自筆証書遺言を作るにあたっては、法律のルールを守る必要があります。
遺言書を訂正のために書き換える場合でさえ、法律はルールを設けています。
このようなルールを守らなければ、せっかく作った遺言も、無効とされてしまいます。
また、文言の書き方次第で、遺言の内容が実現されなかったり、スムーズに実現されなかったりすることがあります。
遺言を、公証役場に手数料を支払い、公証人に作ってもらうこともできます。
これを公正証書遺言といいます。
公証人の面前で、一定の手続きに従って作成されますので、遺言が無効とされる危険性は低いといえます。
ただ、公正証書遺言については、証人が2人必要ですから、秘密保持の点で不安があるとされています。
また、公証人を呼んで、一から遺言を作っていくということはあまりなく、あらかじめ遺言の原案を作ってから、公証人を呼び、手続きを進めることが多いです。
3 専門家のサポート
私たちは遺言の作成を全面的にサポートします。
相続についてのご希望をうかがい、法律のルールにのっとり、トラブルをできるだけ避けられる遺言の案を提示させていただきます。
すでに遺言を作られている場合も、ご相談いただければ、法的視点からチェックさせていただきます。
公正証書遺言をご希望される場合にも、相続についてのご希望をうかがった上で、公証人に伝える遺言の原案を作成させていただきます。
証人2人についても、公証役場と協議して手配することもできますので、秘密が漏れるという心配はありません。
遺言書の保管方法に不安がある場合にも、ご相談ください。
相続が始まった後に、遺言がスムーズに実現されるか不安がある場合には、遺言書で専門家を遺言執行者に指定することも、検討させていただきます。
専門家に相談する際の流れ
1 専門家への相続の相談

専門家に相続についての相談を行う場面は、あまり多くないかもしれません。
そのため、いざ専門家に相談するとなると、どのような流れになるのかについては、疑問に思われる方も多いと思います。
ここでは、専門家に相談する際のおおむねの流れを説明いたします。
2 相談前
相談前については、事前に準備を行っておいた方が、スムーズに相談することができ、専門家からも的確な回答が得られやすいと思います。
例えば、事前に、どのようなことを相談したいかをまとめておくことが考えられます。
まとめておけば、相談の際、すぐに本当に質問したいことを質問することができます。
質問したいことがまとまっていないと、相談時に現状を説明するだけで終わってしまい、本当に質問したいことは質問できず、疑問点だけが残ったままになってしまうおそれもあります。
このような事態にならないようするためには、メモ書き程度のものでも構いませんので、あらかじめ、どのようなことを質問するかをまとめておくことをおすすめします。
また、相続は、前提となる情報が多く、わずかな違いによって結論が大きく異なる傾向にあります。
この点を踏まえると、あらかじめ、親族関係や相続財産についての情報をメモ書き程度で構いませんので、まとめておいた方が良いといえます。
そうそれば、短時間で効率的かつ正確に、前提となる情報を伝えることができるからです。
3 相談時
専門家によって、相談の際の流れは、少々異なります。
相談者から、前提となる情報を伝え、疑問点を伝えた上で、専門家が個別の疑問点について回答する流れになることがあります。
他方で、専門家が重要と考えるポイントを質問し、専門家の側で問題点を指摘した上で、相談者の疑問点に回答するという流れになることもあります。
一概にどちらの形が望ましいと言うことはできず、相談者や相談内容によっても、適切な相談の流れは異なってきます。
当法人は、ご相談いただく際の雰囲気から、最も適切と思われる流れで、お話をいたします。
4 相談後
相談後も、専門家の関与が必要となる場合は、正式に依頼するかどうかを検討することとなります。
この場合は、専門家と協議し、どのような範囲について、どのような費用負担で依頼するかを確定し、正式な委任契約が成立することとなります。
専門家による相続財産(金融資産)の調査
1 金融資産の調査の困難さ

相続財産の調査にあたっては、特に金融資産の調査の必要性が大きいと思います。
これは、被相続人が保有していた預貯金や株式、投資信託、債券について、相続人が相続発生時点で詳細な情報をもっていることは、ほとんどないからです。
相続発生後に被相続人が保有していた金融資産を調査する場合は、どのような調査方法を用いれば良いのか、以下で専門家による金融資産の調査方法の概略を説明します。
2 預貯金の調査方法
預貯金の調査の手がかりは、多くの場合、被相続人の自宅に残されている通帳、証書になります。
通帳、証書が残されていると、その銀行、支店に口座が存在する可能性が高いです。
古い通帳であっても、現在まで取引が続いている可能性があります。
このため、通帳、証書が残されている銀行、支店については、一通り問い合わせを行い、口座の有無と残高を確認します。
その際は、その銀行、支店に、通帳、証書で明らかになっている口座以外の口座が存在する可能性もありますので、すべての口座の有無と残高を照会します。
また、銀行を窓口として、投資信託や債券の取引が行われていることもしばしばありますので、投資信託や債券についても照会の対象とします。
それでは、通帳、証書で銀行、支店を特定することができない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
例えば、他の相続人が通帳、証書を保管してしまっており、その相続人から何らの情報も明かされないことがあります。
また、被相続人が通帳、証書を紛失していることもあるでしょうし、近年ですと、ペーパーレス化により、通帳、証書が発行されていないこともあります。
このようなときは、被相続人の住所の近隣の銀行、支店を一通り調査対象とすることも検討します。
また、銀行で応じていただける場合には、直接問い合わせを行った支店だけではなく、他の支店も含めて、取引の有無を確認します(全店照会)。
3 株式、投資信託、債券の調査方法
株式、投資信託、債券の調査の手がかりは、証券会社から被相続人の自宅に届く、取引残高報告書です。
取引残高報告書が届くと、その証券会社や銀行、支店で取引が存在することが分かります。
また、取引残高報告書の内容を確認すると、報告書発行時点での株式、投資信託、債券の残高を確認することもできます。
株式、投資信託、債券についても、預貯金について説明したのと同じ理由から、残高報告書を確認できないことがあります。
このようなときは、証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求を用いることにより、被相続人が有価証券についての取引を行っていた証券会社や銀行、支店を特定することもできます。
各専門家が協力できることの強み
1 相続分野の特徴

相続分野は、各専門家が協力して対処すべき必要性が高いです。
この点は、他の専門分野とは異なる、相続分野の特徴だと思います。
相続分野では、多種多様な専門家が登場します。
相続人の間で意見の対立があり、協議をまとめる必要があるときには、弁護士が登場します。
相続財産に不動産が存在しており、不動産の名義変更が必要なときには、司法書士が登場します。
基礎控除額を越える相続財産が存在するため、相続税の申告と納付をしなければならないときには、税理士が登場します。
やや特殊な例ですが、農地を特定遺贈によって名義変更するときには、行政書士が登場することもあります。
そして、複数の専門家が登場するときには、各専門家が協力して対処しなければならないケースが多いです。
各専門家が協力することができなければ、相続問題のすべてを解決することができず、最悪の場合、問題が先送りになってしまうおそれがあります。
ここでは、1つの失敗例を紹介し、各専門家の協力の重要性を説明します。
2 協力が不十分な失敗例
この案件では、ある人が遺言の作成を希望していました。
遺言者には子がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となることが予想されました。
遺言者は、所有している土地の1つに、甥夫婦が自宅を建築して使用していたため、この土地を甥夫婦に引き継ぐことを希望していました。
そこで、遺言者は、弁護士に依頼し、遺言書を作成してもらいました。
当時、甥夫婦の父母が存命であり、甥夫婦がいずれも遺言者の法定相続人ではなかったため、甥夫婦に土地を遺贈するとの内容の遺言が作成されることとなりました。
その後、遺言者が亡くなり、甥夫婦は、遺言に基づき、土地の名義変更を司法書士に依頼しました。
ところが、司法書士からは、土地の名義変更をすることはできないとの連絡がありました。
その理由は、以下のとおりです。
甥夫婦が自宅用に使用している土地は、現況は宅地であるものの、地目が畑になっていました。
このため、特定遺贈により名義変更をする場合には、農業委員会の許可を得なければならないこととなります。
農業委員会の許可を得ることができなければ、地目が畑である土地について、特定遺贈による名義変更を行うことはできません。
甥夫婦は、農業関係者ではありませんでしたので、農業委員会の許可を得ることは期待できません。
このような理由から、甥夫婦が取得したはずの土地については、名義変更ができないままとなってしまいました。
3 各専門家が協力する必要性
このような事態を避けるためには、あらかじめ、弁護士と司法書士や行政書士が協議し、どのような遺言であれば名義変更ができるか、検討を行っておくべきでした。
このような検討を行えば、たとえば、生前に地目変更登記を行う等の対処ができたはずです。
以上の例からも、相続分野で各専門家が連携して対処する必要性の大きさがわかると思います。
このため、相続に関する相談をされる場合は、専門家同士の連携に力を入れている事務所にご相談されることをおすすめいたします。
相続人を調査するときの方法
1 相続人の調査がなぜ必要か

相続では、相続人の調査が必要不可欠です。
相続人が限られている場合は、誰が相続人であるかは明らかなので、相続人の調査を改めて行う必要はないのではないかと思われることもあるかもしれません。
しかし、相続では、相続人が誰であるかを第三者に対して証明する必要があり、そのためには、公的記録での調査が必要となります。
たとえば、不動産や預貯金の相続手続きを行う場合には、すべての相続人が書類作成に関与する必要がありますので、法務局や銀行という第三者に対して、相続人が誰であるかを公的記録で証明する必要があります。
もし、些細な調査漏れによって、新たに相続人が存在することが後になって判明した場合には、手続きを最初からやり直さなければなりません。
以下では、公的記録によって相続人を調査するときの具体的な方法について説明します。
2 相続人の調査方法
相続人の調査は、公的記録で行う必要があるものの、事前に、親族関係を把握している親族から、親族関係を聞いておくのが望ましいと思われます。
このような情報を得ておくと、戸籍等の調査を行った際、調査漏れの有無をチェックする手がかりになるからです。
たとえば、戸籍を一通り取得したはずなのに、親族から聞いていた相続人が戸籍に記載されていない場合には、戸籍の取得漏れがある可能性があります。
相続人の調査で取得すべき公的記録は、戸籍です。
戸籍については、市区町村役場で取得することができます。
相続人の調査では、どのような相続関係であっても、共通して、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があります。
被相続人の出生から死亡までで、本籍地の移動(転籍)があったときは、転籍前の戸籍も転籍後の戸籍も取得しなければなりません。
また、被相続人の出生から死亡までで、法改正等による戸籍の作り直し(改製)がなされたときも、改製前の戸籍も改製後の戸籍も取得しなければなりません。
結婚や離婚、養子縁組や離縁等の身分関係の変動があったときも同様です。
さらに、本籍地の変更があり、別の市区町村に本籍地が移った場合には、それぞれの市区町村役場で戸籍の取得の手続きを行う必要があります。
このため、新しい戸籍の記載内容から、その前の本籍地を確認し、その前の本籍地の市区町村役場において、古い戸籍を取得する手続きを行う必要も出てきます。
何度も本籍地が変更されている場合は、いくつもの市区町村役場で戸籍を取得する手続きを行わなければなりません。
被相続人の戸籍以外でどのような戸籍を取得する必要があるかは、相続関係によって違ってきます。
被相続人の子だけが相続人になるときは、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて、被相続人の子の現在の戸籍を取得すれば良いこととなります。
一方で、被相続人に子がおらず、被相続人の父母も存命ではないため、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときは、被相続人の父母の最後の戸籍、被相続人の兄弟姉妹の現在の戸籍も取得する必要があります。
なお、令和6年3月1日から、これらの手続きの負担を減らすために、戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。
広域交付を利用すれば、本籍地に限らず、どこの市区町村役場でも、まとめて請求することができます。
ただし、広域交付で請求できる人には限りがあり、例えば、自分の兄弟姉妹の戸籍は広域交付では請求できませんので注意が必要です。
3 相続人の調査の依頼
以上のとおり、相続人の調査の際には、複数の市区町村役場で戸籍を取得する必要がある可能性があります。
相続関係によっては、何十枚もの戸籍を取得しなければならない可能性もあります。
また、戸籍の内容を精査し、漏れがないかどうかを確認することも必要になってきます。
これらをスムーズに行うために、相続人の調査を専門家に依頼するということもできます。
相続を依頼する場合の専門家の選び方
1 相続に関係する知識を網羅的に把握していること

相続に関係する専門家は様々です。
例えば、相続について、相続人の間で意見調整が必要になった場合には、弁護士が関与する必要があります。
相続税の申告が必要になった場合には、税理士が関与することになります。
相続した不動産の登記が必要になった場合には、司法書士が関与することが多いでしょう。
ここで注意しなければならないのは、多くの場合、それぞれの専門家は、別の専門家の仕事について、詳しい知識を持っているとは限らないということです。
このため、相続では、特定の専門家の知識に基づいて処理を行ったものの、他の専門家から見ると、その処理が適切ではないということが起きやすいのです。
考えられるケースとして、弁護士が相続人の意見をまとめて遺産分割協議書を作成したものの、不動産の登記に詳しくなく、適切に登記を行うことができないといったケースや、税理士が申告のために書類を作成したものの、その書類では、相続人間の意見が適切に調整されていないといったケースが起こり得ます。
このように、相続では、他の専門家の知識も含めて、網羅的に把握している必要があります。
2 相続についての詳細かつ最新の知識をもっていること
相続では、事案のわずかな違いによって、どのような処理をすべきかが大きく変わってきます。
不動産の名義変更1つを取っても、遺言に「相続させる」と記載されているか、「遺贈する」と記載されているか、遺言執行者が指定されているかどうか等によって、登記申請の仕方が変わってきます。
参考リンク:法務省・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
このような事案のわずかな違いを踏まえて、どのような処理をすべきかについて、詳細な知識をもっておく必要があります。
また、相続では、様々な分野で取り扱いの変更が起きています。
例えば、先ほどの不動産の名義変更が義務化されたことは記憶に新しいですし、近年では、相続法の改正により、配偶者居住権の制度が新設されたり、遺留分の計算方法が変更されたりもしました。
他にも、農地法上の許可が必要な範囲が変更される等、様々な場面で取り扱いの変更がなされています。
このような取り扱いの変更に対応するためには、様々な分野についての最新の知識をもっておく必要があります。
3 相続を依頼する場合の専門家の選び方
以上のことから、相続の場面では、網羅的、詳細かつ最新の知識を持ち、これを活用することができる専門家に依頼するべきでしょう。
そのためには、相続問題に特化しており、様々な士業と連携して適切な判断をすることができる専門家へ相談することをおすすめします。
連絡がとれない相続人がいる場合の対処方法について
1 連絡をとることができない相続人がいる場合の問題点

相続の手続きは、相続人全員の合意に基づいて行う必要があります。
銀行、証券会社等で相続の手続きを行う場合も、基本的には、相続人全員の実印の押印と、相続人全員の印鑑証明書の提出を求められます。
このため、連絡をとることができない相続人がいると、基本的には、相続の手続きを進めることができないこととなってしまいます。
それでは、どうしても連絡をとることができない相続人がいる場合は、どのようにすれば手続きを進めることができる状態を作ることができるのでしょうか。
2 相続人の住所の調査
⑴ 住民票や戸籍の附票を取得
このような場合には、相続人の住所の調査を試みることとなります。
相続人の現在の戸籍をすでに取得しているのであれば、これを手がかりに、相続人の住民票や戸籍の附票を取得することが考えられます。
住民票については、相続人の住所がある市区町村役場が、戸籍の附票については、相続人の本籍がある市区町村役場が取り扱っています。
もっとも、住民票も戸籍の附票も、取得することができるのは、本人、同一世帯の人等、一定の人に限られています。
このため、相続のために必要があると説明しても、市区町村役場でこれらの書類を取得することができないという問題が発生する可能性があります。
⑵ 弁護士に依頼することも
住民票や戸籍の附票は、弁護士等が職務を行うのに必要な場合には、職務上請求によって取得することができます。
そのため、どうしてもこれらの書類を取得できない場合には、弁護士等に依頼して、相続人の住所の調査を行うことも考えられます。
住民票や戸籍の附票により相続人の住所が特定できた場合には、これらの住所宛に手紙を送付する等し、連絡を試みることが考えられます。
3 相続人が住民票上の住所にいない場合
⑴ 相続人が所在不明だったとき
現実には、相続人が市区町村役場で住所変更の手続きを行っていないため、住民票上の住所で生活していないことがあります。
このような場合には、住所上の住所に手紙を送ったとしても、「あて所に尋ねあたりません」として、手紙が返送されてしまいます。
たとえ、このように相続人が所在不明であったとしても、相続人が現実に存在する以上は、その相続人が合意しなければ相続の手続きを進めることはできません。
では、相続人が所在不明である場合には、どうすれば良いのでしょうか。
⑵ 不在者財産管理人を選任
相続人が所在不明である場合には、相続人の代わりに法的な当事者となる不在者財産管理人を選任し、手続きを進めることを試みることになります。
参考リンク:判所・不在者財産管理人選任
不在者財産管理人は、家庭裁判所で申立を行い、選任してもらいます。
なお、不在者財産管理人の選任にあたり、家庭裁判所は、警察に対し、捜索願いが出され、所在の調査が行われた記録があるかどうか、職業安定所に対し、登録がなされているかどうか等の調査を行います。
これらの調査の結果、相続人の所在が判明し、相続人に連絡をとることができるようになることもあります。
家庭裁判所の調査を経ても相続人の所在が判明しない場合には、正式に不在者財産管理人が選任され、相続の手続きを進めることができるようになります。
相続財産(不動産)の調査方法
1 固定資産税の納税通知書を確認する

亡くなった人名義の不動産については、固定資産税の納税通知書で確認することができます。
固定資産税の納税通知書は、毎年4月から5月にかけて、各市町村役場から、不動産の名義人に対して送付されます。
この通知書は、亡くなった人が不動産を所有していた市町村ごとに送付されますので、固定資産税の納税通知書が届くと、その市町村に亡くなった人が所有していた不動産が存在することが分かります。
固定資産税の納税通知書には、固定資産課税明細書という名前のページがあり、亡くなった人が所有していた不動産が、一覧表で記載されています。
したがって、このページを確認すると、亡くなった人名義の不動産を、網羅的に確認することができます。
2 固定資産税の納税通知書を紛失してしまった場合
固定資産税の納税通知書を紛失してしまった場合には、市町村役場において、固定資産課税台帳と呼ばれる書類を取得することにより、亡くなった人名義の不動産の一覧を取得することができます。
固定資産課税台帳は、名寄帳と呼ばれることもあります。
なお、不動産には、固定資産税が非課税となっているものが存在します。
公衆用道路やため池等がこれに当たります。
先に述べた固定資産税の納税通知書には、非課税の不動産は記載されていないことがあります。
他方、固定資産課税台帳や名寄帳には、非課税の不動産も記載されています。
こういった理由から、非課税の不動産も漏らすことなく確認する目的で、固定資産課税台帳(名寄帳)を取得することもあります。
3 登記事項証明書を確認する
以上の方法で亡くなった人名義の不動産を確認することができたら、各不動産の登記事項証明書を取得します。
固定資産税の納税通知書や固定資産課税台帳、名寄帳には、その年の1月1日時点の所有不動産が記載されています。
その年の1月1日以降、相続の時点までに、不動産の権利移転があると、不動産の所有者が変わっていることがあります。
このように、相続の時点における各不動産の名義人を確認するために、各不動産の登記事項証明書を取得する必要があります。